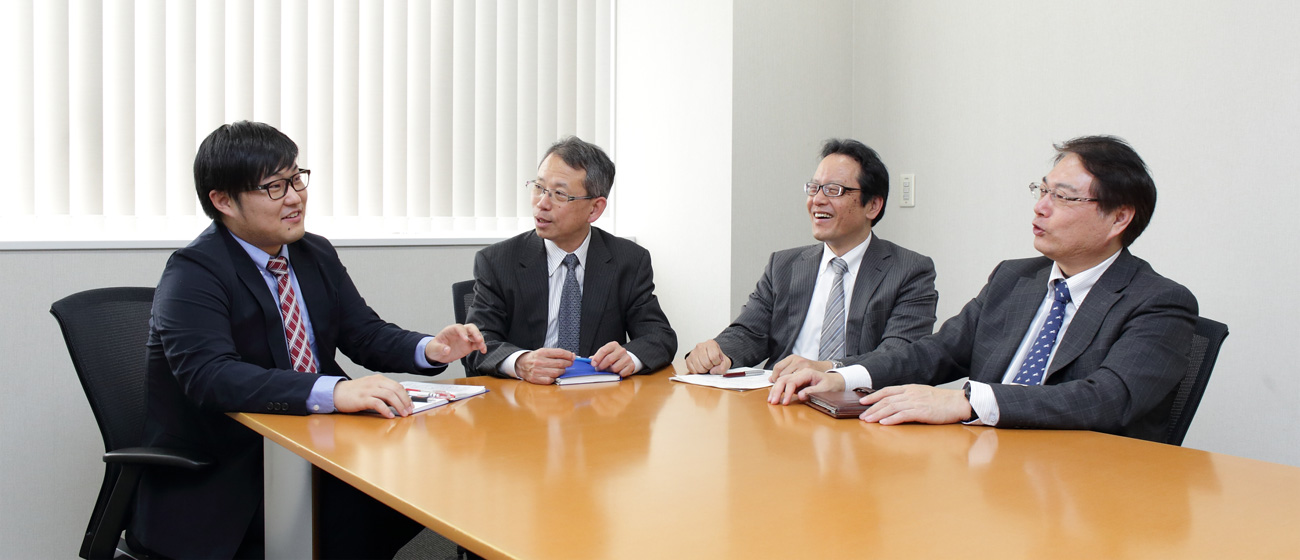製品の品質を高めると共に
新しい価値としての
「サービス」を展開

- 庭田 孝一郎
- 品質保証部 部長

- 林 憲彦
- マーケティング事業本部
ショベル営業本部
カスタマーサポート部 部長

- 森 三朗
- マーケティング事業本部
クレーン営業本部
クレーンCS部 部長

- 大谷 拓也
- マーケティング事業本部
クレーン営業本部
クレーンCS部
海外サービスグループ
※部署名・役職は取材当時のものです。
品質やサポートを新たな魅力に


- 大谷品質保証部やCS(カスタマーサポート)部門の意義や役割をお聞かせください。

- 庭田では、まず品質保証部から。会社の目指すものとしては、顧客満足度の向上というのが最大の目標だよね。そこに向かって開発・生産・サービスの各部門が連携しながら、チームワークで取り組んでいくのだけど、全体の流れの中で各部署を支えるのが品質保証部の役目だ。

- 大谷全ての工程に品質保証部が関わるということですよね。

- 庭田そう。我われは3つの品質を保証する役割があるんだよ。1つ目は「ねらいの品質」。どんなものをつくるかということで、開発部門と連携する。2つ目が「出来映えの品質」。生産部門との連携だね。3つ目が「対応の品質」。これはサービス部門との連携。これら全ての品質を見て、責任を持つのが我われの仕事なんだ。そしてこの先は、4つ目と言ってもいいかな、「会社の品質」も見ていこうとしているところだよ。営業・サービス部門はもちろん販売会社とも連携して、受注の段階から会社そのものの品質にも責任を持って、より安心と信頼を高めていこうと考えているよ。

- 大谷CS部門はいかがでしょうか。

- 森サービス部門の仕事は製品を販売した後の事後処理業務、つまりアフターセールスサービスと思われがちだけど、本質はもっと広い。お客さまに製品を効果的・効率的に使っていただけるように、さまざまなサービス活動を通じて支援するのが仕事だ。「商品」というのは「製品+サービス」で成り立つんだけど、多くの部署はお客さまに新車を手渡したところである意味役割が終わるけど、サービス部門はそこから始まる。クレーンは一般的に20~30年使われるので、その間ずっとお客さまとのお付き合いがあるよね。それだけに大切なポジション。我われの仕事は、コベルコ建機の印象を決めるくらい重要な意義を持っているんだよ。

- 林我われCSが、いま取り組んでいる仕事は大きく3つある。第1に、お客さまの機械の修理やメンテナンス。第2に、お客さまの機械の部品交換やシステムの追加などで販売利益を生み出すこと。そして第3が特に力を入れている部分で、社内外サービススタッフ全体のレベルアップを図るための教育や仕組みづくり。研修設備などハード面から、カリキュラムなどのソフト面まで整備して、サービススタッフのスキルアップ教育をしているよ。特に海外ではサービス行政といって仕組みづくりにも取り組んでいる。長期に渡ってユーザーになってもらうために、サービス面からもコベルコ建機のファンを増やそうということだね。

- 大谷製品の性能に加えてサービスの内容や質も、コベルコ建機を選んでいただく魅力のひとつにするということですね。

- 林そうだね。お客さまのサポートという意味では営業部門とも協力するんだけど、お客さまの抱える課題に対して、新しい機械の導入によって経営戦略的な側面から支援するのが営業部門で、エンジニアの立場から機械をケアすることでサポートするのがサービス部門の仕事、と言ってもいいね。

- 大谷品質改善においては、どういった役割やプロセスがありますか?

- 庭田基本は、サービス部門とも連携してトラブル対応を1件ずつ解決していくことだよ。次にそういったトラブルの内容を整理して、原因をみつける。そうやって集まった事例から全体をつかんで、設計・開発部門や生産部門にフィードバックして再発防止や品質改善に役立てている。現場で起こる小さなことを見逃さず、でも広く捉えることがとても大事で、商品力とものづくり力を上げていくためには非常に重要だよ。

- 森デスクワークでは見つけられない、現場でなければ出合わないいろんな事象があるから、現場で得られるものは大切だよ。データベース化も進んでいるし、技術者としてはその原因の探求にやりがいを感じるよね。問題解決能力が問われるところだ。

- 庭田品質改善というのはパズルゲームみたいなものだね。答えは必ずあるわけで、たくさんの可能性の中から知識や経験の力で探っていくおもしろさがあるよ。そしてその情報を社内で共有していくんだ。

- 林新機種の開発も、設計のときにサービス側の意見や現場の情報を取り入れることで、より品質の高いものができるんだよ。

- 大谷コベルコ建機の強みや優位性はどういうところだと思われますか?

- 森グループ企業が多いことは有利な点だね。神戸製鋼グループには、鉄鋼・アルミなどの材料部門、機械部門、エンジニアリングや研究施設などもあるから、連携によってより広い視野と深い知識を得られていると思う。さらに、それぞれが持っているサービス部門とも互いに協力したり、情報交換ができているよ。

- 林社風としては、社内の風通しがいいね。地区の壁もないし、メーカーと販売会社の壁もない。フラットな関係で、互いに意見が言いやすい。サービスの人が他部署に意見を言えないと、それはとても大きな損失だよ。稼働中の機械の情報やお客さまのニーズ・課題は、サービス部門が持っているからね。

- 庭田ただ仲良くするということでなく、意見を言い合える。これは最大の強みだよ。部門の壁や、年齢の壁がない。もともとコミュニケーションが盛んな上に、ジョブローテーションで他部署の仕事の理解も進んでいるから、意見交換が活発なんだ。企業によっては部署が違うと管理職同士で話さないと何も進まないということもあるだろうけど、うちでは状況によって担当者間で調整をするから現実的だし、スピーディだよね。

- 大谷確かに。私も必要に応じて、他部署の人と直接話しますね。
活発な情報交換が生む高品質



- 林品質保証やサービスは、情報の溝ができるとスピードや精度が落ちるので、コミュニケーションの質が現れやすいところだと思う。コベルコ建機のサービスはよくなったと言われるけど、この気質から生まれた成果じゃないかな。

- 森うちの会社では、「上司の許可はもらったのか?」というセリフを聞かないよね(笑)。他の部門の担当者が私のところに直接訪ねてくることも多いね。

- 庭田フラットな組織というのは、もちろん良い面だけではないけど、若い人がどんどん意見を言えるとか、意欲を持って働きやすいというのはあるよ。
「MADE BY KOBELCO」の次世代サービス


- 大谷品質保証やCSがこれから目指していることや目標などを聞かせてください。

- 森新車販売で新しいお客さまやシェアを増やすのは、ある程度までいくと限界が来る。となると次の成長エンジンはサービスなんだよね。サービスで顧客満足度を上げる。さらに、お客さまの経営上の課題やニーズを次の商品に反映させて、リピートしてもらう。だから会社としてもサービス部門にはますます力を入れるよ。現在も、遠隔監視システムを搭載して、故障やトラブルが起きる前に部品を交換する予防保全などを取り入れているけど、これからはさらにICTやIoTなどの活用で、次元の進んだサービス体制をつくりたいね。

- 庭田コベルコ建機のものづくりは「MADE BY KOBELCO」をスローガンに、世界共通品質を目指す活動を進めているけど、品質保証というのはものづくりとサービスが両輪だから、改めて「MADE BY KOBELCO」を考えたいと思っている。どこでつくっても、どこで買っても、均一な高い品質というのを、サービスにも適用したい。海外のお客さまに対しても、日本と同様のサービスをだれでも提供できるようにしていくよ。

- 林製造拠点や流通網などは海外にも広がっているけど、サービス体制はまだ十分整っていなくて発展途上。いま、まさに攻め込もうとしているところだから、サービスの海外展開はこれからぐんぐん伸ばしていくよ。若い社員もどんどん海外に行って、プロジェクトを動かしている。会社のチャレンジの波に乗って、自分でいろいろな新しいことができるから、楽しいと思うな。

- 大谷私もこの前、ドバイに行きました。とても勉強になりました!

- 庭田海外サービスもデータベース化を進めているし、ICTを使って故障の予兆を掴むこともできるようになったけど、なにかあったら直すのは人だから。サービスマンの教育支援などの現地サポートも必要だし、現場に行かないと分からない情報もあるし、これからは海外が忙しいと思う。

- 林トラブル対策についてはナレッジシステムの構築も進んでいて、スマホアプリでトラブルシューティングもできるようになっているけど、これからはもっと進化させて、アプリで撮影(録音)したデータを分析し原因が分かるようにしたいと考えている。教育も、今後はVRやARなどの活用も視野に入れているよ。

- 森例えばクレーンは、現在67カ国に販売していて、国内外で14000台が稼働しているんだ。そこに2万人のオペレーター(24時間稼働など一台の機械を複数のオペレーターで稼働)がいるわけ。その方たちとダイレクトにコミュニケーションがとれるインターフェイスを検討している。そういった時代が早く来ると思っているよ。自動翻訳とかも導入して、たくさんの国々のオペレーターと直接対話ができる仕組みがあると、トラブル対応力も情報収集力も格段に上がるよね。

- 大谷アプリとか自動翻訳とか聞くと、若い人が得意な気がしますね。

- 林そうだね。ICTに限らず、若い人には思い切ってチャレンジしてほしいし、コベルコ建機にはそれができる環境があるよ。

- 大谷会社の未来の話ですが、私自身の将来を想像して、わくわくしてきました。これからが楽しみです。